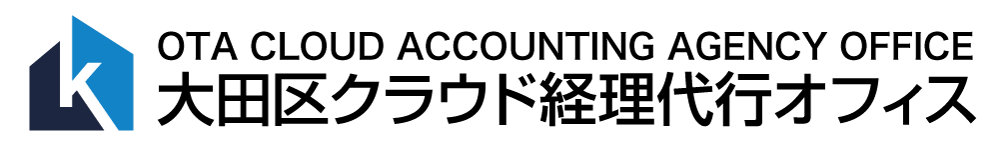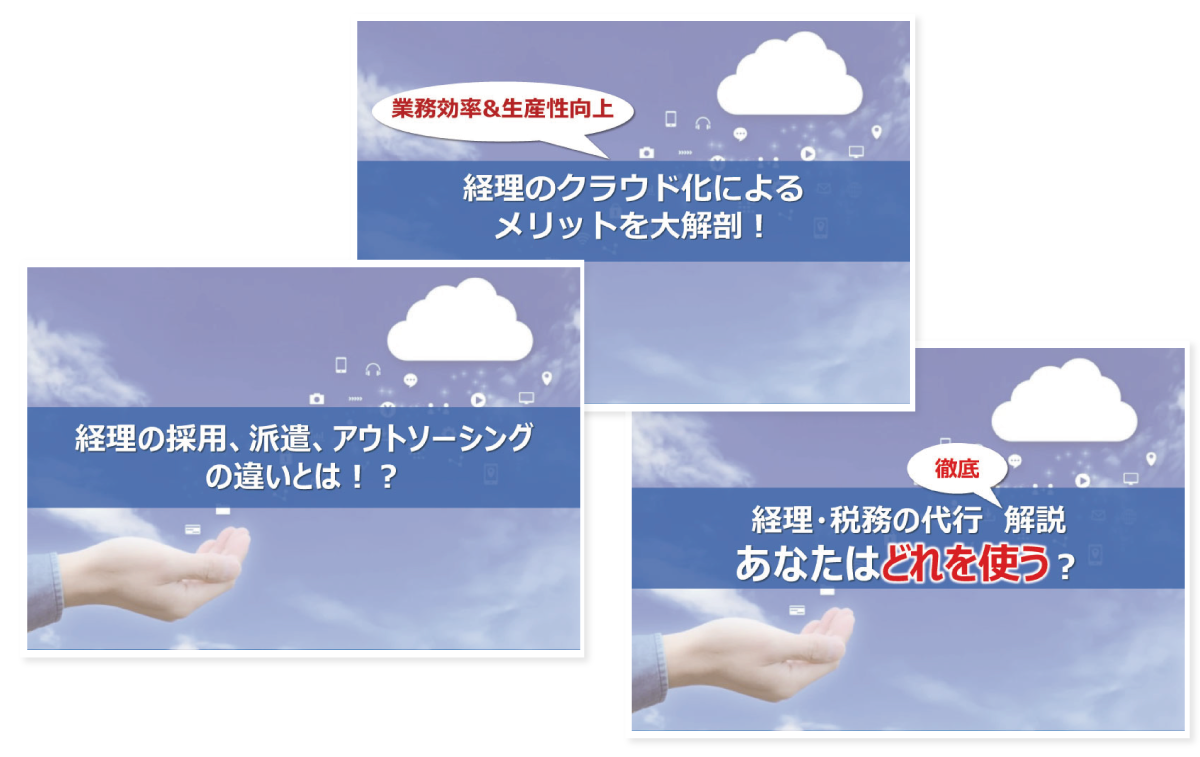令和6年分確定申告書の変更点を詳しく解説!~定額減税や住宅ローン控除のポイント~
令和6年分確定申告書の変更点とは?
令和6年の所得税及び復興特別所得税の確定申告書では、定額減税に関する新たな記入欄が追加されました。
具体的には、第一表の右側中央にある44番の欄に「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」という項目が新設されました。この欄には、適用される人数と減税額を記入する必要があります。
また、その下の45番には、定額減税後の所得税額を記入する欄が設けられました。ただし、赤字申告となる場合は「0」と記入しなければならないため、注意が必要です。
第二表にも定額減税に関する変更が追加
第二表の「配偶者や親族に関する事項」内にある「その他」の欄にも定額減税に関連する変更が加えられました。
昨年までは「調整」と記載されたチェックボックスが存在し、「控除を受けていないが所得金額調整控除の対象となる者」にチェックを入れる形式でした。
しかし、今年からこの欄が「その他」に変更され、控除対象ではないが所得金額調整控除を受ける場合には「1」、申告者の定額減税の対象となる扶養親族である場合には「2」と記入する形に変更されました。
この「2」の記入対象となるのは、控除対象扶養親族や同一生計配偶者であり、「1」に該当する場合は「2」の対象外となるため、この1つの欄で十分に対応できるよう工夫されています。
住宅ローン控除の特例対象個人とは?
第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄には、「住宅」のチェック欄が新設されました。この「特個」という部分にチェックを入れるケースは、「特例対象個人」に該当する人が対象となります。
「特例対象個人」として認められる条件は、以下のいずれかに該当する人です。
- 年齢が40歳未満で、配偶者がいる場合
- 40歳以上で、40歳未満の配偶者がいる場合
- 19歳未満の扶養親族がいる場合
これらの条件を満たす人が、令和6年に住宅を取得して住宅ローンを組む場合、通常よりも借入限度額が上乗せされ、控除額が増加する可能性があります。
また、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」にも、この「特例対象個人」の種別を記入する欄が新設されており、確定申告時にはこの書類の記入漏れがないようにしましょう。
まとめ
令和6年の確定申告書には、定額減税や住宅ローン控除に関する重要な変更点がいくつか加えられています。特に、第一表・第二表に新設された記入欄や、住宅ローン控除の特例対象個人に関するチェック欄の追加など、変更点をしっかり把握し、適切に申告することが大切です。
これらの変更点を理解し、正しく申告することで、適用できる控除を漏れなく受けることができます。確定申告の準備を進める際は、今回のポイントを参考にしてください。
補足と解説
国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】
この申告書を添付してあげるとより分かりやすいです。
令和6年分特別税額控除
控除の概要
合計所得金額が1,805万円以下である居住者の方が適用を受けることができる控除(定額減税)
第一表
44欄 … 控除額の合計額を記入します。
なお、「人数」欄の□には、あなたを含めた控除の対象となる人数を記入します。
第二表
「 配偶者や親族に関する事項(20~23、34、39、44)」欄…同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、「その他」欄の□に「2」を記入します。
所得金額調整控除との区別(PDF20ページ目)
所得金額調整控除(10 ページ)の(1)のFの金額がある場合で、かつ、扶養親族が他の納税者の扶養親族又は同一生計配偶者とされており、あなたの「扶養控除」又は「障害者控除」の対象とならない扶養親族であって、特別障害者又は23歳未満であるとき(※5)には「1」を記入します。
また、あなたの定額減税の対象となる扶養親族である場合には「2」を記入します。
特例対象個人(PDF20ページ目)
住宅借入金等特別控除又は子育て対応改修工事等に係る住宅特定改修特別税額控除において、あなたが特例対象個人(40ページ)に該当する場合で、扶養親族が19歳未満であり、他の納税者の配偶者控除又は扶養控除(「住民税」欄の16に〇を記入した扶養親族を含む。)の対象とされているとき
なお、上記に該当し特個に〇を記入する場合で、扶養親族が国外居住親族であるときには、「国外居住」欄の□に「5」を記入します。
令和6年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書