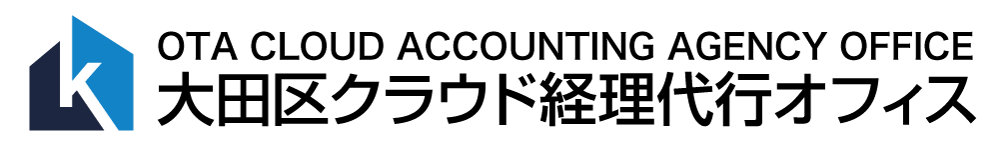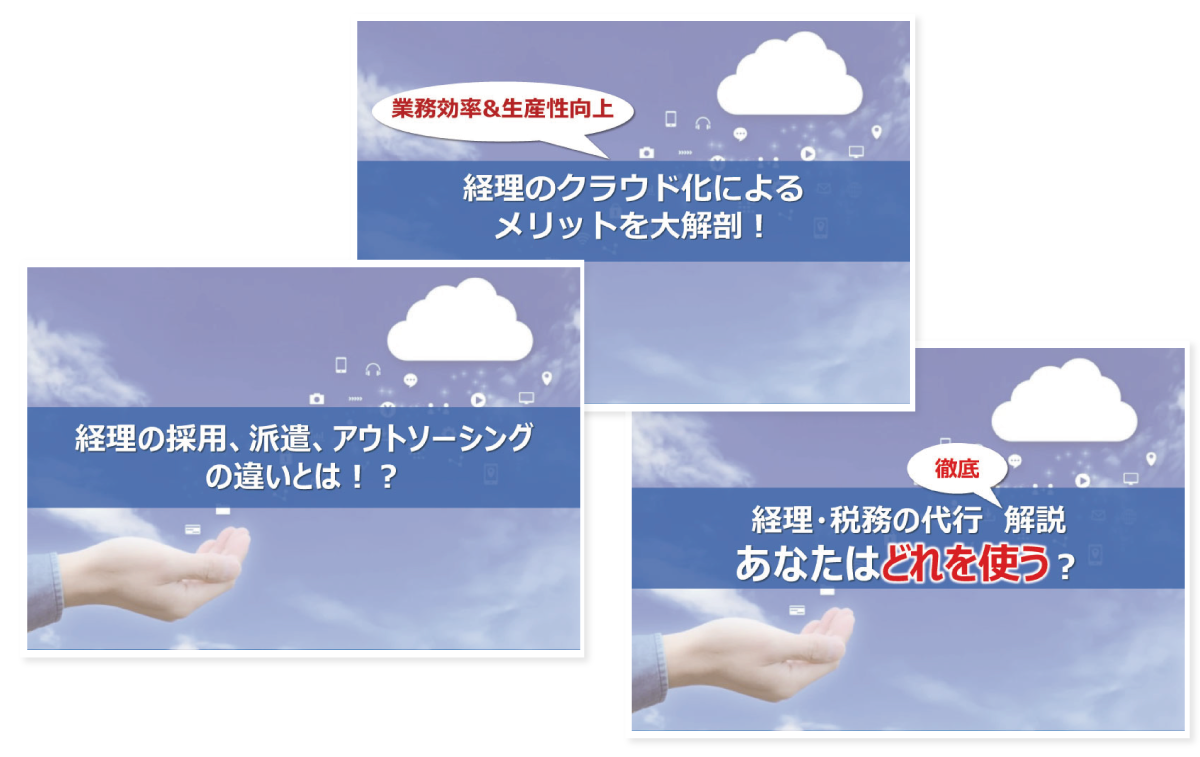中小企業におけるリース会計と法人税の実務対応ガイド
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!
最近、「リース取引の会計処理や法人税への影響がわかりにくい」という声を多くの中小企業の経営者様や経理担当者様からいただきます。
リース契約は設備投資の選択肢として非常に便利ですが、会計や税務の処理が複雑に感じられることも多いですよね。
この記事では、中小企業が直面するリース会計と法人税の処理方法について、具体的にわかりやすく解説しています。
上場企業と中小企業での違いや、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースそれぞれの扱いの違いも丁寧に説明します。
この記事を読むことで、「リース取引の種類ごとの会計処理」「法人税との関係」「今後の制度変更への備え」についてしっかり理解できるようになります。
この記事は、主に以下のような方におすすめです:
- 中小企業の経理・財務担当者の方
- 設備投資を検討している経営者の方
- 税理士や会計士との連携に備えて知識を深めたい方
リース契約とは「所有せずに利用する」しくみ
リース契約とは、他社が所有する特定の資産を、契約期間中リース料を支払うことで使用する契約です。
例えば、月額10万円で5年間コピー機を利用する契約などが該当します。資金繰りの観点からも、
支出が一度に発生しないため、設備導入の選択肢としてよく活用されています。
私が担当しているある中小製造業のクライアントでは、数百万円の機械設備をリースで導入することで、
初期コストを抑えて事業拡大につなげていました。
実際、こうした資金繰りの柔軟さが、リース契約の大きな魅力です。
上場企業はすべて「売買処理」に統一された
上場企業や大企業では、新しいリース会計基準が適用され、ファイナンス・リースもオペレーティング・リースも原則として「売買処理」が必要になりました。
これは、リース取引が実質的に資産の取得と変わらないという考え方に基づいています。
例えば、資産計上して減価償却を行い、リース負債を貸借対照表に計上することが求められます。
こうした制度変更は、投資家や金融機関に対する財務情報の透明性向上が目的です。
中小企業は従来どおり「賃貸借処理」が可能
一方、中小企業に対しては「中小企業会計指針」や「中小企業会計要領」が適用されており、
ファイナンス・リースであっても賃貸借処理が認められています。
つまり、資産計上やリース負債の記録は不要で、リース料を経費として処理する方法が今も選べるのです。
実際に、ある顧問先の建設業者では、高額な重機をリースで導入しており、
毎月のリース料を費用計上する形で運用していました。現場単位のコスト管理がしやすく、
会計処理もシンプルで済むことがメリットです。
法人税の処理も上場企業と中小企業で異なる
上場企業では、ファイナンス・リースを「売買処理」で取り扱うため、
リース資産を減価償却し、利息と元本を分けて処理します。
ただし、法人税の計算上、会計と税務で処理が一致しないため、別途「申告調整」が必要になります。
一方、中小企業においては、法人税の面でも賃貸借処理をそのまま適用できます。
つまり、リース料をそのまま損金として処理することが可能で、資産計上や減価償却の計算が不要です。
さらに、令和7年度の税制改正大綱では、オペレーティング・リースについても
「債務の確定した部分の金額を損金算入する」と明記されており、
従来の賃貸借処理を継続できる方向性が示されています。
まとめ
リース会計と法人税の取り扱いは、企業の規模によって大きく異なります。
上場企業では「売買処理」が求められますが、中小企業は「賃貸借処理」の選択が可能です。
これは、資金繰りの柔軟性や経理負担の軽減につながる重要なポイントです。
この記事を通して、リース契約に関する制度の違いとその実務的な対応策を明確に理解できたと思います。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。
参考資料
国税庁タックスアンサーNo.5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分) 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm
中小企業の会計に関する検討会 「中小企業の会計に関する基本要領」平成24年2月1日
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/about/download/0528KaikeiYouryou-1.pdf
公益社団法人リース事業協会 「新リース会計基準について-借手側の会計処理-」2024年12月
https://www.leasing.or.jp/studies/docs/shinkaikei20241209_01.pdf