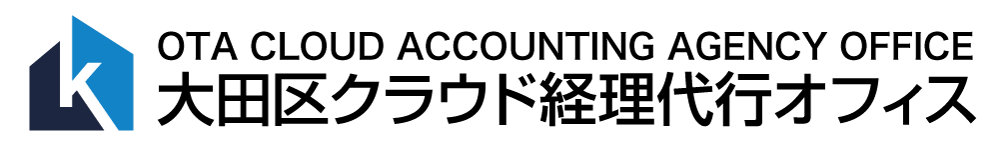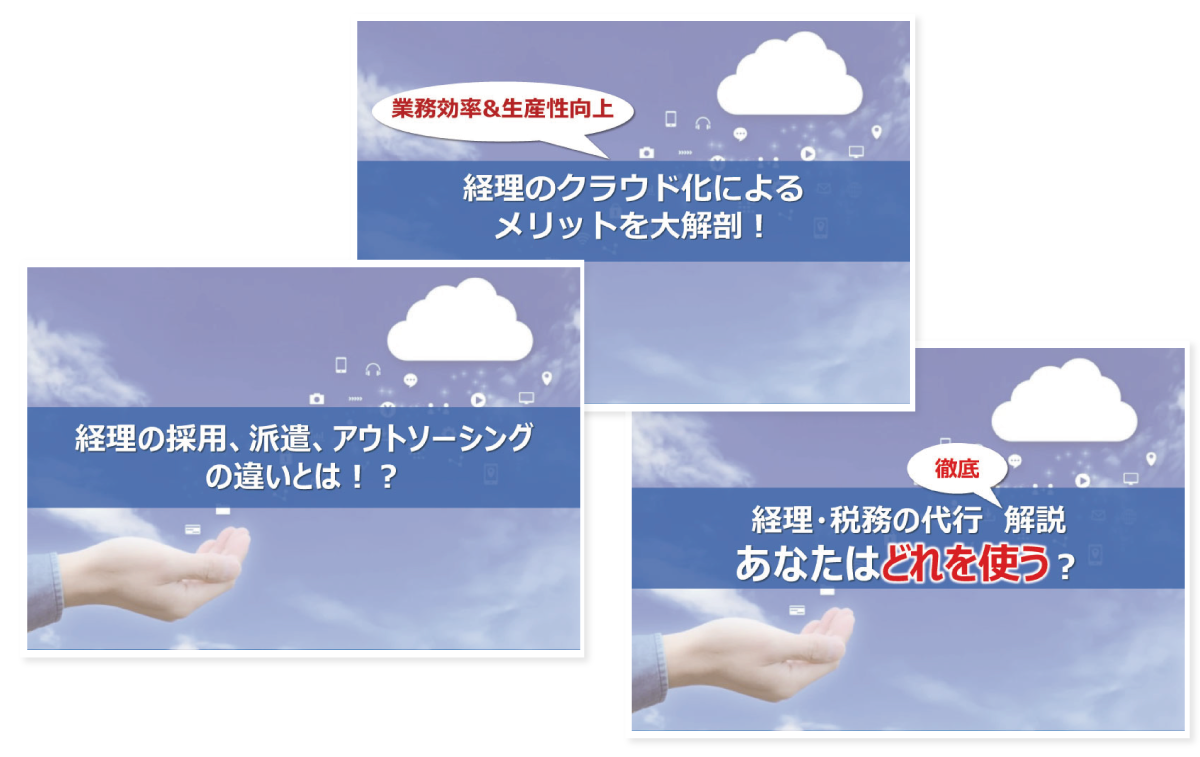暦年贈与信託とは?相続対策として活用するポイントを税理士が解説
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!
相続対策を検討していると、「生前贈与を活用して相続税を減らせる」と耳にすることがあります。
しかし、最近の法改正により「生前贈与加算期間」が延長されるなど、制度の理解がより重要になってきました。
暦年贈与をより確実に活用する方法として、「暦年贈与信託」という仕組みも注目されています。
この記事では、暦年贈与信託を活用した生前贈与の方法や、注意すべき税制改正のポイントをわかりやすく解説します。
加えて、連年贈与による課税リスクや、贈与の心理的・生活的影響についても触れていきます。
相続税対策を進めたい方、生前贈与を検討している方、子や孫に資産を移したいと考えている方に、この記事は特に役立ちます。
生前贈与の魅力とは何か?
生前贈与には、将来の相続財産を減らす効果があります。相続税の節税につながると同時に、子や孫など次の世代が資産を早い段階から有効活用できるメリットもあります。
例えば、私の顧問先でも、お孫さんの教育資金や住宅資金に充てるために毎年一定額を贈与しているケースがあります。
贈与を受けたお孫さんが大学進学費用を自分で賄えるようになったというエピソードは、私自身も強く印象に残っています。
【変更点1】生前贈与加算期間が7年に延長される
令和6年1月1日以降の贈与については、相続税の計算時に加算される期間が、これまでの「相続開始前3年以内」から「7年以内」へと段階的に延長されます。
具体的には、令和8年12月31日までの贈与は3年間の据え置きですが、それ以降は1年ずつ加算対象期間が延長され、最終的には令和13年から7年となります。なお、延長された4年間分については、贈与財産のうち合計100万円までは加算対象外です。
【変更点2】暦年贈与信託で贈与を計画的に行う
贈与の方法として、信託銀行が取り扱う「暦年贈与信託」を活用する方法があります。
この仕組みでは、贈与者が信託銀行と契約し、金銭信託の形で贈与額や贈与先、贈与時期を指定します。
例えば、複数の子や孫を候補者として事前に登録しておき、毎年贈与する相手と金額を選びます。
その後、信託銀行が贈与者・受贈者の意思を確認し、信託財産から金額を送金します。
贈与税は、基礎控除110万円を超える部分に対して課税されます。
また、信託商品によっては、受益者の名義変更を伴うタイプなど、商品設計に差があるため、契約内容の確認が重要です。
【注意点】連年贈与・定額贈与に対するリスク
毎年同じ金額を贈与し続けた場合、それが「定期金給付契約」とみなされ、初年度にまとめて課税される可能性があります。
国税庁の事例では、10年間にわたり毎年100万円を贈与する約束をした場合、合計1,000万円に贈与税が課されることになります。
暦年贈与信託では、毎年受贈者や金額を選び直すため、このリスクを軽減できます。
ただし、形式的な確認だけでなく、実質的に「都度の意思確認」がなされているかが重要です。
【生活面の影響】贈与による家族への影響も検討する
贈与は金銭的な問題だけではありません。例えば、若い世代に毎年のように資産が移転されると、その生活が「贈与頼み」になってしまう可能性もあります。
実際に、あるご家庭では、息子さんが贈与に依存するようになり、働く意欲が薄れてしまったという相談を受けたことがあります。
資産移転のメリットとデメリットのバランスを考えることも、贈与を成功させる鍵です。
まとめ
生前贈与は、相続税の節税だけでなく、次世代への資産承継としても非常に有効な手段です。
しかし、法改正による加算期間の変更や、連年贈与リスク、贈与信託の選定といった多くの注意点もあります。
しっかりと制度を理解し、税理士など専門家に相談しながら進めることが大切です。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。
参考
国税庁「(令和6年1月1日以後に贈与を受ける方へ)
令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/030.pdf
No.4402「贈与税がかかる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm