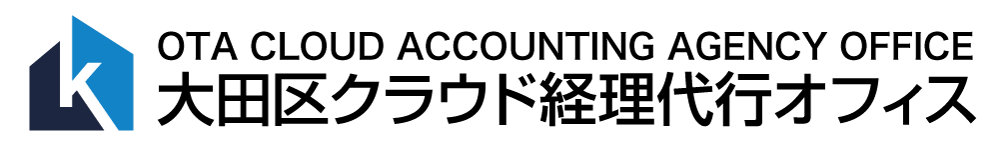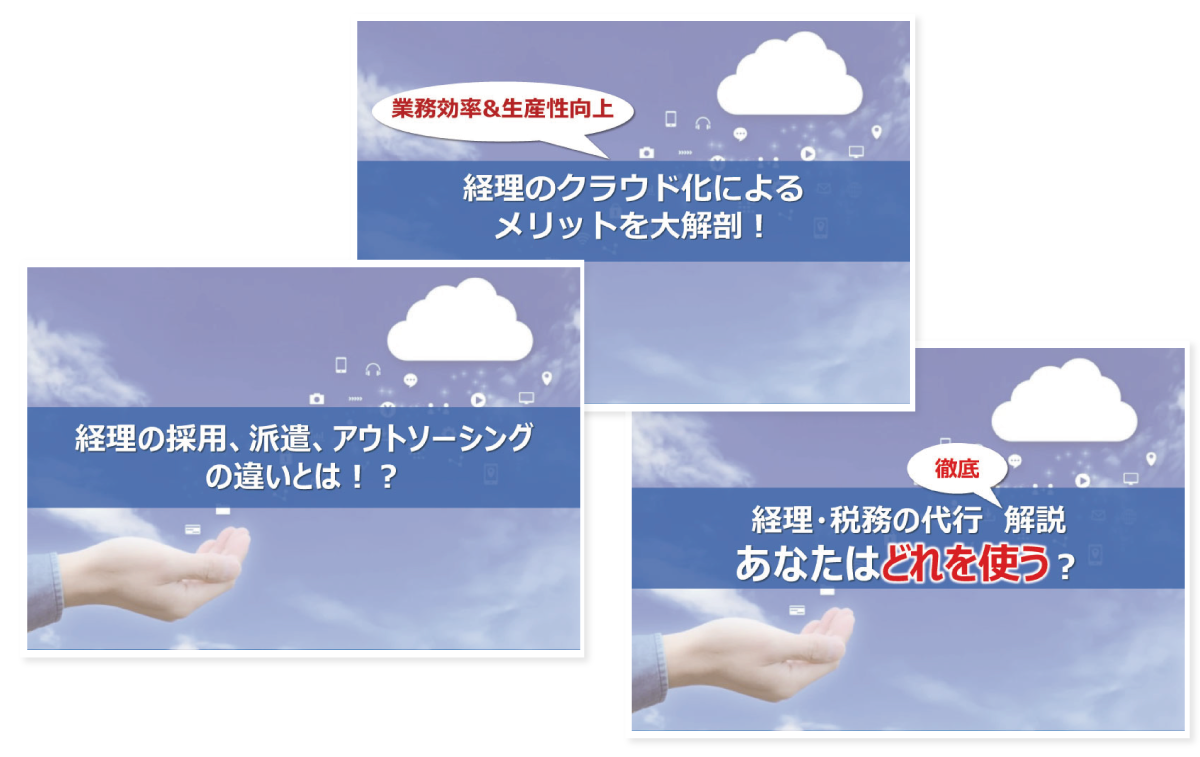定額支払いのインボイス対応|口座振替で顧問料・家賃を支払う場合の3つの対策
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!
毎月、事務所の家賃や士業への顧問料などを、銀行口座から自動的に支払っている方も多いのではないでしょうか?
「金額が固定だから請求書のやり取りは不要」と思っていた方も多いと思います。
しかし、インボイス制度が始まった今、「定額だからOK」という考え方だけでは対応が不十分になる可能性があります。
特に、インボイス発行事業者との取引においては、仕入税額控除を受けるために適切な書類の保存が求められます。
この記事では、口座振替によって定期的な支払いを行っている場合に必要なインボイス対応の方法について、3つの具体策に分けて詳しく解説します。
制度変更にどう対応したらいいか不安な方でも、読み終えるころには、どの選択肢が自社に最適なのかが明確になります。
この記事は、
✅ 顧問料や家賃を口座振替で支払っている事業者の方
✅ 経理や税務の業務に関わっている方
✅ インボイス制度における実務対応を知りたい方
に、特におすすめの内容となっています。
口座振替で支払う定額費用、インボイスはどう対応すれば良い?
毎月決まった金額を、銀行口座から自動的に引き落として支払うケースは非常に多くあります。
たとえば、月額10万円の事務所家賃や、税理士への月額5万円の顧問料などが該当します。
これまでは「金額が毎月同じ」で「契約で決まっている」ため、通帳の記録があれば請求書の発行は省略されることも多く見られました。
しかし、インボイス制度が始まったことで、「インボイス(適格請求書)を発行・保存していないと仕入税額控除ができない」というルールが明確になりました。
これにより、「これまで通りのやり方」が通用しなくなるリスクがあります。
インボイス対応の基本は「保存できるかどうか」
インボイス制度に対応するには、「インボイスの記載要件を満たす書類を保存する」ことが必要です。
記載要件とは、発行事業者の名称や登録番号、取引金額、消費税額など、税法で定められた情報のことです。
具体的には、次の3つの方法から選ぶことができます。
対応策① 毎月インボイスを発行してもらう(原則)
最も基本的な対応方法は、「支払先に依頼して、毎月インボイスを発行してもらい、それを保存する」というやり方です。
特に、複数の支払先がある場合や、毎月の取引内容に変動がある場合には、毎月発行の方が記録の正確性も高く、おすすめです。
ただし、支払先が個人事業主や小規模な法人である場合、発行の手間を嫌がられることもあるため、事前の相談が重要です。
対応策② インボイスを一定期間ごとにまとめて発行
毎月インボイスを発行するのが難しい場合、「半年ごと」や「年1回」のまとめ発行でも、インボイスとして認められています。
「1年間のインボイスを年度末にまとめて発行してもらう」という対応をしている場合もあります。
税務調査でも、この方法で問題になることは少ないため、一定期間のまとめ発行は現実的な対応策といえるでしょう。
対応策③ 契約書や通帳など複数の書類を組み合わせて保存
少し応用的な方法ですが、「契約書」と「通帳の記録」などを組み合わせて、インボイスの記載要件を満たすことも可能です。
| インボイス記載事項 | 対応する書類 |
|---|---|
| ①事業者名、②登録番号、③取引内容、④消費税額、⑤受領者名 | 契約書 |
| ⑥取引年月日、⑦取引金額 | 通帳の振替記録 |
この方法は、インボイスの発行そのものを省略できるため、支払先とのやり取りが最小限に抑えられるというメリットがあります。
覚書などの追加書類でも対応可能
契約書を締結し直すのが難しい場合でも、「覚書」などの追加書類を作成することで、記載要件を補うことが可能です。
注意点として、契約書に「月額〇〇円(税抜)」という表現がある場合、消費税法上のインボイスとしては不十分になる可能性があります。
可能であれば、「税込金額」や「消費税率の明記」がある契約書が望ましいです。
また、支払先が途中でインボイス発行事業者を辞退するケースもあります。
定期的に国税庁のインボイス登録サイトで確認し、最新の登録状況を把握するようにしましょう。
まとめ
この記事では、口座振替による定額支払いにおけるインボイス制度への対応策を3つに分けて紹介しました。
- 原則は、毎月インボイスを発行してもらう
- 現実的な対策として、半年~年1回のまとめ発行も可能
- 応用的な対策として、契約書や通帳を組み合わせて保存する
制度に対応しつつ、業務の負担を減らすためには、取引先と柔軟に相談しながら、自社に合った方法を選択することが大切です。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。